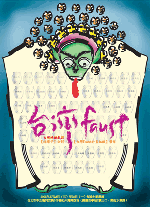公共性の痒みについて
六張○にある公墓1950年代に処刑された多くの人たちのうち二百数名の遺骨が埋められている墓地を訪れたとき、私たちを待ちかまえていたのは蚊の大群だった。訪れる人も少ない、倒木と雑草の荒れ地の守備兵のように、蚊の大群は大軍となって私たちを襲ってきた。雑木の枝葉が墓地を覆い隠し、陽光を遮る。いや、その闇の溜まりは実は光を避けているのではなく、光を吸い込んでいるのではないか。蚊と格闘しながら、そのような想念が沸き上がる。重力が強すぎるために時計は一向に進まず、時間が凍結しているのだ、と。
尋常ではない蚊の痒みは<死者の痒み>という妄想に私を駆り立てた。痒みとは皮膚や粘膜の痛点に作用する弱い刺激であるとすれば、置き去りにされたこの死者たちの時間とは、外部から備給される弱い刺激の中にあるといえるのではないか。この死者の時間は忘れられたのではなく、その時々の生者の都合によって召還されたり、再び棺桶に封印されたりするのだから。
人間の脳の中にある海馬という器械は、記憶の製造工場である。無数に近い外部からの情報をここで処理して、それを記憶とするか無視するかを決定するらしい。この決定に際しては、以前の記憶が参照とされる。どの記憶を参照とするかは、扁桃体という感情記憶器械が大きな影響力を持つ。感情記憶の意向に沿って、海馬は無数のネットワークを通じて古い記憶を召還し、記憶を作り上げる。だが、古い記憶は新しい記憶に破壊されるのではない。一度、記憶となったものは鋳型のままに脳の片隅で存在し続けるのだ。だから、古い記憶は有用性のあるかぎり、たえず神経細胞の独房と海馬の間を往還している。古い記憶は往還という行為を強制されるという意味で、たえず外部からの弱い刺激を受けているのだ。
その古い記憶が痛みの記憶だとすれば、それは忘れられたわけではなく、絶えず弱い刺激の中に晒されている。それが痒みという感覚ではないか。
<新公共性>というそれ自体は何も語っていない言葉をめぐって考えを巡らせる時、まず現在私らが棲息している<公共性>とはこの痒みのことではないか、という想念がやってきた。<民主主義>という、東と西の、南と北の、双方の眼差しの交差によって、かろうじて命脈を保っている制度内に<市民>という耳障りのいい名前で存在することは、<痒い>のである。私らは、まるで私ら自身がすでに古い記憶であるかのように、その時々の社会の中に召還されたり独房に蟄居したりしているように思えてならない。ただの参照枠として自分が存在しているように感じるのだ。
いや、参照としている主体が制度ではなく、自分自身であるというトートロジーも成立するだろうが、それは問題ではない。問題ではないぐらいに、<公共性>という中で、私らと制度は二つで一つである。もはや分節できないのだ。
<アジア>という地域に限定しても、どの地域においても<民主化>にいたる過程は苦難であり、それは激しい痛みであった。痛みは私らの暮らしと行動を制止し時間を凍らせるが、同時に、激しくその痛みからの脱却をも希求させるものであった。だが、痒みは私らに<掻く>という作業を要求する。掻き続けるという作業である。それが消費社会を生きる<市民>の身振りではないか、と私には想われる。何かを消費し続けなければ私らは存在できない。そのような自分らの身振りが、<掻く>作業であるように感じられるのだ。
私にとって、今回の「台湾Faust」というテント劇場の場所性は、<掻く>身振りの中に、<痛み>を再度召還しようとする行動である。
(後半部紛失)
東アジア「冷戦」が構成した文化の差異
桜井大造・陳映真対談(翻訳整理:胡冬竹)
(解説)この対談は、今年三月二十三日からの六日間、台北市内で公演されたテント芝居『台湾ファウスト』を書き演出した演劇家、桜井大造氏と、その『台湾ファウスト』を観劇した台湾作家、陳映真氏との対談をまとめたものです。この『台湾ファウスト』の道具立ては、実際に獄中生活を体験した陳映真氏の小説『趙南棟』にヒントを得たもので、その縁から今回の対談が実現されることになりました。『台湾ファウスト』は、戒厳令が解除された後にも、その後遺症としての白色テロの記憶に折り合いをつけられない台湾の現状を反映しつつ、そういった台湾人の精神状況への問いかけを含む挑戦的な内容を持つものです。この対談は、戦後の日本と台湾の文化環境の違いを浮き立たせつつ、しかしそれ自体が「冷戦」によって構成された「複数の現実」であったことを確認する舞台となりました。
(小説『趙南棟』は、白色テロ被害者の女性が獄中で生んだ赤ん坊の名前――監獄の建物「南所」に因んだ名に由来する作品。現在『季刊・前夜』[影書房、二〇〇五年春号以降]にて訳出が始まっている。)
桜井:今日は、『台湾ファウスト』を見ていただいた陳映真さんに、感想を伺うというのが主要なる目的できました。昨今の台湾の文化状況との関連で忌憚のないご批評を伺えると幸いです。
陳:まず、私は演劇に関しては、詳しくないです。その原因については、このあいだ既に桜井さんにちょっとお話しました。戦後台湾の文化領域の中で、演劇は非常に弱くなった。それ以前の三十年代の抗日戦争時期、そして四十年代には、演劇の領域ではいずれにしても左翼が力を持っていて、左翼系の演劇団体が一気に現れたため、その圧倒的な人気が国民党に焦りをもたらしたのです。国民党は当時、演劇の影響をとても恐れて、台湾にやってきたら、演劇に対して徹底的なコントロールを行った。台湾で、自由に脚本を創作し、演劇活動をすることが許されなくなった。だから、私個人的として、自分の「文学青年時代」に二つのものを見失った。一つは「現代詩」。私は最初文壇と関係を持ち始めたころ、当時の台湾はモダニズム文学の天下で、自分は古本屋で禁書との出会いをきっかけに、左翼文化理論に接触することになりました。それで、モダニズム文学に対して、抵抗感を持つことになりました。後で徐々に分かってきたことですが、モダニズム文学にも二つの種類があって、その中には革新的なものもあった。しかし、当時の台湾ではやっていたモダニズム文学は特殊で、当時五十年代のアメリカ「冷戦文化」の背景にして輸出された芸術形式としての絵画、詩などでした。実際に、五十年代の台湾では、レットパージの旋風で、三十年代の進歩的な文学理論が消滅していた。血生臭いレットパージの土壌の上で、アメリカからのモダニズム文学が三十年代の文学理論に取って代わったのです。もちろん、第三世界でもモダニズム文学で抵抗しようとする動きもあったが、たとえばネルーダなど。
ちょっと自信のない見方ですが、私が知っているテント芝居というのは、日本の六十、七十年代の安保闘争の時代に生まれ、先天的に日本が日米安保体制に追随することに対する反発があるように思われます。このようなテント芝居の歴史と性格について、もし桜井さんに教えていただけると幸いです。ついでに言うと、抵抗的な内容であるわけですが、どうして「非現実主義」的な手段をお取りになっているのかも、教えていただきたい。桜井さんの演劇は外見から見ると、実験主義(experimentalism)と思われがちで、いわゆるモダニズムの傾向を持っているように見えますが、実際は決してそれだけではない。なぜかというと、桜井さんの演劇では理念性がとても強い。モダニズムの最大の特徴は理念を否定すること、主題を否定することによって芸術の絶対的な純粋さを追求するものです。しかし、桜井さんの演劇はたくさんの重要なことを話そうとする。簡単にモダニズムに分類されない。とは言え、桜井さんの演劇はモダニズムのなかによく使われるイメージも見られる。たとえば、死亡、死体、狂気、死体の腐臭、ゴースト(幽霊)、血など。しかし、桜井さんはこういうイメージを道具として使いつつも、決して目的化していない。ここはとても興味深いことです。そこでお聞きしたいのは、もし演劇の目的として啓蒙であるのだとしたら、大衆(日雇い労働者)に向かい合ったときに、重要な理念をどういう形で表現するわけですか?どうしてテント芝居を、最初からこのような形を選んだのですか?
戦後台湾に生まれた私が見失ったもう一つのものとは、つまり演劇でした。私たちは劇団をもつことさえ許されなかった。小劇団みたいに、芝居のセットを持って活発的な演劇活動をする、そんな可能性はなかった。だから、冒頭述べたように、私は演劇に対して門外漢であり、ほんのわずかの幼稚な感想を踏まえて、今日は大造さんに教えていただきたいところです。
桜井:60年代後半に始まった日本のテント芝居は歴史化される程の激しい契機を持っていませんので、歴史というよりは簡単な推移だけを紹介します。しかも、これはまったくの私見です。僕は73年にテント芝居を始めて三十年以上続けています。でも、これは演劇表現としてテントを使用するということではなくて、特に当初は旅するための手段としてのテントの使用でした。ですから「演劇表現」というものから「流れ者芝居」へと逸脱するためにテントが選ばれたのです。「テント演劇」ではなく「テント芝居」という言い方でずっとやってきました。
六十年代後半に、私たちより先んじてテントでの表現を始めたのは60年安保世代の先輩たちです。60年代の日本は、大衆レベルでモダニズムが浸透し、特に東京オリンピックをきっかけにして、大安売りされた「セカイ」が突然こちらに飛び込んできた。それまでの貧乏くさい庶民が急に市民に昇格して、スーパーで「セカイ」を手にとって買える、というような幻想が始まったのだと思います。
それはたとえば劇場空間にもすぐに反映してきます。文化資本が新規参入してきます。しかし、これは旧来の商業演劇とは違うものです。演劇を商品化するのではなく、演劇をイメージ化して消費社会の戦略に寄与させようとするものだからです。また、戦後から続いた民衆劇場的な新劇の手法はだんだん通用しなくなる。とくに新劇の社会主義リアリズム的な手法は消費都市型劇場では通用しなくなった。このような環境の中で、アンダーグラウンド演劇というものが出てきました。その一つの方法がテント演劇です。ですから当初のテント演劇はそのような消費社会の中で出てきたものです。もちろん、ベトナム戦争の渦中ですから、米国に追随し続ける日本政府に対する抵抗という要素は内在していたと思います。たしかに、前近代に遡行する表現も多かったし、はっきりと文化運動を揚言した黒テントという集団もあります。
後発した僕らは、これら先達たちへの批判から出発しました。一つは「表現」というものへの捉え方です。先達たちはなんやかや言っても「表現」が重要なのです。これに対して「表現」というのは幻想だ、というのが若かった僕らの考えでした。何かを表現しようとか、それをだれかに見せるとかは、とてもブルジョア的な考え方だと感じていたわけです。もう一つは、市民社会的な環境に抵抗しているようで実は順応しているアングラ表現者という存在に対する反発です。彼等は実は裏返しのエリートではないのかという疑問がありました。僕らの集団のほとんどは学生大衆闘争の経験者でした。70年代以降、学生闘争が衰退し、とはいっても社会復帰できるような気分もなく、どこか逃走する場所が必要だったのだと思います。選ばれたのは<旅>でした。テントはそれを実現する場でした。ある種の避難所だったのですね。当初は、トラック一台にテントと人間を積んで公演地も決めずに出かけました。田舎の町に行って、空き地を見つけテントを建てた。そして、近所の人たちにチラシを配って歩いて公演しました。昔の放浪する芸能者の真似をしたのです。それは僕らのテントの出発点だった。それは73~74年のことですね。
戦後すぐの新劇運動で「トランク劇場」とか「めざまし隊」などがあったと聞きますが、ある種これに近いかもしれません。ただ、僕たちには本隊がないし、何かを啓蒙するということでもなかった。何しろ、劇場性を破壊するための劇場ですから、観客にはいい迷惑だったかもしれません。
陳:ブレヒトも劇場を破壊することを提唱しましたね。
桜井:新劇は、ブレヒト劇とロシアのスタニスラフスキー・システムの2つが主な路線だったと思います。徐々に「新劇」運動は制度化していきます。「労演」組織があって、それがルートを作る。職業演劇化するわけです。職業化の陰に日本共産党や日本社会党の方針が垣間見える。60年安保以降、新左翼の登場と同時にこの構造に批判的な演劇人が登場してきます。
陳:中国(大陸)でも、演劇運動は党の指導のもとに行われていました、当時の「地下党」のもとで。しかし中国では、日本のように左翼文化の中からの内省という文脈は見られなかった。その原因を考えると、日本の共産党は、中国共産党のようにわりと順調に勝利を収め、人民の支持を得るような状況を持たなかったためでしょう。
桜井:六十年代は、中国の文革も含めて、世界中で旧来の制度や文化に対する疑問が噴出してきた時代だと思っていました。しかし、同世代の台湾人に話を聞くと、60年代から70年代は、「家庭は工場だ」という標語のもとで、学校から戻ると家族そろって内職していた、ということでした。60年代学生反乱などというのは、中国を除けば、「先進国」セカイの体験なのだと知りました。そのことは、今回台湾で芝居をやるときに、強く前提にしなければならなかったことです。
陳:六十年代の台湾でごく少数の人に限り、アメリカ留学経験を通して、左翼運動の影響を受けて、外の世界に驚かされた。どうして世界中で毛沢東を再評価する風潮が盛んになったのか。天安門広場、周恩来、江青の「模範劇」などの映像が北米のテレビで流された。そして、尖閣諸島返還運動(沖縄返還に際し、尖閣諸島の所属を日本のものとしたアメリカ合衆国に対する異議申し立て)が起こり、五十年代のレットパージ以来、台湾の思潮は初めて、左傾化することになった。当時のアメリカでも、中国革命関連の読書サークルが盛んになって、中国三十年代の書籍が研究されるようになり、思想的に大きな変化が現れた。五十年代から六十年代までは、台湾で「反共抗ソ」の文学以外で、一番影響力を持っているのはモダニズム文学だった。そのモダニズム文学の影響を受けた若者たちがアメリカに渡り、68年左翼運動の衝撃を受け、モダニズム批判に乗り出したのです。1970年から1974年にかけて、台湾でも「現代詩批判」運動が起こり、おもにモダニズム的な詩を否定する動きとなった。この運動を経て、その後の「郷土文学論争」の中で、私たちは四十年代の文学伝統を再発掘することに至ったわけです。私個人の場合には、偶然古本屋で四十年代の書籍と出会って、そして一人淡水(台北郊外)のあたりでトランジスタラジオを聴いた。そのときに、中国全土は赤色に染められ、志気高揚だった。また、ソ連共産党と中国共産党の論争も聴いた。当時、ソ連共産党と中国共産党の論争がそれぞれ放送され、私は布団の中でそれを全部聴いた。どうしてわざと淡水に行ったかというと、淡水は大陸により近いため、よく聞き取れるためだった。そういう意味で、台湾も間接的な契機で文革と接したといえるでしょう。
桜井:淡水でラジオを聴く陳映真さんの姿を想像してみると、何とも言えず格好良いですね(笑)。
さっき、陳さんから出された演劇における啓蒙の話ですが、僕がテント芝居を開始した段階ではすでに啓蒙という考えはありませんでした。伝達という要素はもちろんあるわけですが、少なくとも、知識人が大衆と向かい合うというような感覚はまるでありません。むしろ知識人性を激しく否定していましたし、実際に知識人としての訓練を積んでもいませんでしたから。新左翼も含めて左翼性の中には啓蒙というのが重要であるのでしょうが、僕らにはなかった。
陳:具体的な課題に即して言いますと、演劇としてのテント芝居を労働者に見せることは可能なのか、実際に伝わると思いますか?
桜井:伝わると思います。私たちは77年くらいから90年くらいまでは、東京の山谷や横浜寿町、大阪の釜ヶ崎――日雇い労働者の街(寄せ場)でやったわけですね。上手にやらないと物は投げられるし、女優がでたら、みなわぁーと言って、舞台に出てくる。労働者が女優を抱きしめたりする。私たちは、女優を防衛しながらセリフを言わせなければならなかった。それは、ものすごく直接的な感じだったので、知識人と大衆みたいなテーマで悩む余裕もなかった。なにしろ労働者と取っ組み合いで「芝居」を奪い合うわけですから、まさにそこが伝達の場でした。僕たちの側も必死ですから、どうあっても伝えなければならないものだけがピュアに現れます。僕らのメンバー自体が、ほとんどが日雇い労働者かそれに近い暮らしでした。僕自身も四十歳近くまでは日雇い労働者だった。現場の仕事をやっていると、テント設営はどんどんうまくなる。そして、日雇い労働者の仲間が手伝いに来ます。それは、ある種の「日雇い労働者文化」のようなものでした。だから、啓蒙という言葉は、僕らのテント芝居には存在しなかった言葉です。むしろ、70年代以降、日本では啓蒙というのはマスメディアの方法論となったのではないかと思います。メディア報道やコマーシャリズムはそれまでの60年代をものすごく上手に奪ったのです。だから、私たちは啓蒙もしないし、また自分も啓蒙されないようなテントをやるしかない、と思ったのです。
陳:これは、すごくショックを与える発想ですね。桜井さんの公共性に関する文章(『台湾ファウスト』の公演に付随して発表された文章「公共性についての痒み」)を読んだときもそう感じた。間違いなく、資本主義が発展すればするほど、公共性は制度化され、そして平均化される。桜井さんは、この文章の中で公共性の中の主体性の問題を論じましたが、面白かったのは、その「痛み」と「痒み」の弁証関係でした。しかしそのような考えは、どこから見ても知識人的な考えじゃないですか。大衆にとっては、難しいでしょう。どのようにしてそれを、芸術の形式で大衆に語ることができるでしょうか。私が言っている「啓蒙」は、大衆を説教することではない。ブレヒトが言ったように、芸術、文学、演劇などは大衆の生活から生まれたものであるが、しかし決して生活そのものにとどまらず、表現するときに生活を揚棄したものとして現れる。何故かというと、その表現は生活を凝縮して、大衆に生活の中の矛盾を伝えるからです。現代の公共性というならば、高度な消費主義の市場の中で、人々は自分が市民あるいは公民であることを自任するかもしれないが、実際は市場に翻弄されるものすぎない。どのように人々をその幻想の中から喚起するかということは、まさに桜井さんのこの公共性についての文章の中からヒントをいただいた。この喚起する作業はけっして容易ではないが、このすばらしい考え方を芸術の形で大衆に送り返して、そしてまた大衆の反応からさらに反省をまとめることが課題と思います。私も、決してエリートが大衆を啓蒙することを主張していません。
桜井:「公共性についての痒み」という文章は、たしかに普通の人にとって難しいかもしれない。僕は文章がへたですから、どうも硬くなります。きっと、普通の人は読んでもわからないかもしれません。しかし僕にとっては、それでいいのです、書くものに関しては。ただ、芝居に関しては、伝えられるような芝居をしているつもりです。テント建築予定地の周囲に住んでいるお婆ちゃんや普通の暮らしを送っている人たちに触れて、その人たちの顔を思い浮かべながら台本は書きました。あまり豊かではない暮らしをしている人たちには絶対伝わるはずだ、と思いながら書きました。たしかに難しい言葉も使っています。でも、その言葉は次には必ずギャグの対象にしています。前の難しい言葉をひっくり返す言葉を必ず用意して、そのひっくり返しによって、前の難しい言葉がクリアに立ち上がる、そういう手法を使っています。書物を読むのとは違いますから。観客はそのひっくり返しのおかしさを起点にして、その前の難しい言葉を思い起こすのです。だから、難しい言葉の意味そのものではなくて、それを巡る構図を一瞬捉えることができるのではないか。そういう意味で分かるはずだと思います
陳:もちろん、私は演劇に関しては詳しくないですが、確かに文学に関しても同じ問題は存在します。創作者は一つの理念を持っている。しかし、理念そのものをそのまま人に伝えるわけいかないから、やはり、いろいろな工夫が必要です。たとえば、私が『山道』、『鈴鐺花』を書いたときにもそうだった。そのとき、まだ戒厳令の時代で、まさに自分が表現したい理念をそのまま書いてはいけないから、さまざまな工夫をしながら、自分が言いたいことを書きとめた。ここでは、自覚的に芸術性を揚棄することが求められるでしょう。そこに、桜井さんの創作方法と共通しているところがあると思います。お婆さんたちに馴染みがある芸術形式、民間演劇の形式はやはり伝統的な形が多いと思われる。芝居だったら、物語の始めと終わりがあって、人物関係がはっきりしている。桜井さんはご自分の方法でやっていらっしゃることは、ちゃんと自分なりの理屈があると思います。ブレヒトも必ずしも伝統的な形を取っていないし、断裂、跳躍、芝居の幻覚を潰して、直接に観客と対話するような形を取ったりしていました。私は、ある特殊な創作方法にこだわるのではなくて、演劇の効果に関心を持っています。ブレヒトの方法を簡単に説明すれば、こういうものになるでしょう。つまり、「私は今芝居をしていない」という感覚。人を感動させようとする芝居と違って、ブレヒトは最初から舞台の幻想を破り、生活のなかの矛盾に目覚めさせることを目指した。たとえば「公共性」について、台湾の知識人の間で、それをうまく説明できる人はそんなに多くない。この「公共性」という言葉を芝居のセリフの中に持っていく際に、もちろん、いろいろな解釈があると思いますが、桜井さんの「公共性」の文章ほど、深刻ではなくなるのではないか。
桜井:ブレヒト演劇の「異化効果」で僕が感じているのは、それが方法論としてまるごとナチスに奪われたということです。ブレヒトが挑んだものは、大衆を覚醒させることであったでしょが、それがそのまま大衆の熱狂の側に反転したのではないかということです。ナチスの三十年代の10万人規模の即興演劇集会は、ブレヒトを援用していると思います。「効果」を問題にした場合、こういうことが必ず起こるのではないか。僕は、芝居というものにむしろ「効果」を求めません。稽古や舞台の準備をして、一定の場を作りますけど、そこで何が起こるかということに関しては、予想をつけません。むしろ予想のつかない眼差しを場が持ち始めることを注視しています。だから、作品性というものからは遠いのです。
陳:おっしゃったことは、大体わかりました。いろいろ疑問を持ちながらも、その日実際桜井さんのテントで芝居を見たときに、三時間に及ぶ芝居で舞台が白けることがなかったことに、とても感心しました。今の観客はそう簡単に喜ばないものだから。つまらなく感じたら、すぐに帰っちゃいますよ。三時間の芝居をじっとみて、存分に笑わせたことは、芝居の力を証明しているでしょう。桜井さんはわりと実験主義的な手法を使っているが、結果を見ると、この手法で観客に興味を持たせることが決して不可能でないことがわかります。みんなそれぞれテント芝居空間に入る入り口が違うかもしれないが、三時間の白けることがない芝居を維持することは大したものだと思います。もう一つの発見は、桜井さんが本当の芸術家であること。その後、脚本も拝見させていただいたが、とても詩的で美しかった。印象深いところもたくさんあった。たとえば、処刑される前に赤ちゃんに乳を飲ませるシーンを読んだときに、思わず目が潤ってしまった。今も鮮明に覚えていますが、幾つかの詩的なソロのナレーション。桜井さんは文学的で、詩人ではないかと思わず考えてしまった。桜井さんは、いつも今回のように、ちょっと急ぎ足で創作せざるを得ないのですか。おそらく、台湾での公演の原因もあってそうなったのでしょうが、もし、もっとリハーサルの余裕をもつことができれば、もっと良かったかもしれない。
桜井:過分にお誉めいただいて恐縮します。芝居は陳さんの観られた2日目から随分と動いて、昨日の5日目でかなりクリアになってきました。稽古が不足していたのは、その通りですが、これはアマチュア演劇の宿命です。特に、今回の集団の集まり方は変わっています。僕が誘った人は鍾喬と王墨林だけです。この二人も役者はほとんど経験が有りません。自然といろいろな縁で集まったのです。17人の俳優のうち経験者は半数くらいです。生まれて初めてという人が半数です。一つの芝居の中で、17人のキャラクターを使って、全部組み合わせるのは相当に難しいです。全員が主役でなくてはいけないし。でも不可能ではありません。その俳優たちのことを伝えようという意志が強ければ、何とか頑張れるのです。だから、演劇的な資質などは関係なく、その人が何故芝居の場に立つのか、どんなカラダに変化する可能性があるのかを知ることが重要です。その人の言葉にならない意志を僕が翻訳して、何とかその場で生かそうとするわけです。もちろん、ほとんど誤読・誤解ですが、翻訳しようとしたこちらの意欲があれば、その誤読は稽古場で次の美しい誤読を産みます。もしも、詩的な部分があるとすれば、その人を書くときの誤読・誤解の中の苦しみが融けたときに、ふっと言葉が露出したのだと思います。僕の中から単独で詩が生まれたわけではないのです。
陳:『台湾ファウスト』についてもう一つ感じたのは、「ファウスト」を素材にしたものが、文学や演劇の領域でたくさん再生産されている。無限の知識を求め、自分の命(魂)でそれを交換するテーマですね。しかし、桜井さんの『台湾ファウスト』は、完全にその因襲的なテーマ性を破ることで元の物語はそれほど目立たなくなるが、桜井さんの独自のファウストの味が現れることになった。先もすこし述べましたが、役者たちがもっと稽古を重ねれば、芝居の全体的な効果ももっと上がったでしょう。
桜井:たしかにその通りです。ただ、テント芝居の場合、稽古に回す時間が少なくなるのです。台湾の参加者は、テントについてあまり経験がないから舞台作りはなかなか進みませんでした。それと、最初に、重い物を運んだり、穴を掘ったりすること、つまりカラダを汚すことに慣れていないということもあります。それで予想より舞台作りに時間が取られて、稽古が十分ではありませんでした。でも、参加者のカラダはこの1月で相当変わったと思います。みんな汚れ仕事をいやがらなくなりました。5年前、台湾で演出したとき印象的だったことがあります。テントの入り口に砂が積まれていて邪魔なので、それを1メートルぐらい先のところに移してくれるように頼んだのです。すると、すぐに携帯電話をかけて業者を呼んだのです。たった1メートルですよ。でも、それは昔のことで、今はみんな本当によくカラダを動かすようになりました。
陳:この芝居についての感想をもう一つ述べたいです。六張タ逡謦n(白色テロ被害者の無縁仏)のことです。僕は当時六張タ逡謦nを発見した三人の中の一人だった。政治犯とされた人たちと一緒に墓地で草刈をした。少しずつ少しずつ、三つのエリアで二百ぐらいの墓碑を発見した。桜井さんの芝居の一番初めのところで、墓地のシーンが出てきましたね。それは僕にとって、ものすごいインパクトを持ちました。そしてもう一つ、芝居の中でときどき監獄、壁、「門がない(No Exit)」のシーンが出てきて、それも僕にとって強い衝撃だった。牢屋の中に一つ門があるが、しかしこの門は牢屋にいる僕(囚人)にとってなんの意味もない。看守が外から門を開けなければ、門は開かない。そして、もうすぐ処刑されるお母さんが赤ちゃんに乳を飲ませるシーンなど――僕みたいな牢屋生活を送った人にとって、本当に泣かせるものだった。だから芝居が終わったときに、ずっと立って拍手していました。
桜井:そういうシーンは、まさに陳さんの作品『趙南棟』から啓発されたものです。
陳:そして、その死刑犯が処刑される直前に目を覆う布を拒否するシーン、手錠を外すことを断るシーン、目の前の川を凝視するシーンなど――小説の中に書いたことがあるので、感無量です。
桜井:僕は馬場町(白色テロ時代、政治犯を処刑する場所)に行ったときに、しばらく目の前の川を眺めるとそういう処刑された人の様子が幻視されてきました。それは観客と共有できる白色テロへの普通の感覚です。また、藍博洲さんが『幌馬車の歌』で書かれている死刑囚を送るシーン、房室から一斉に合唱が起こる場景。今回の芝居の中では、死刑に赴くのは女たちで、「メイフェイ眉飛サー色ウ舞」(顔が喜びに輝くという意味、メフィストと掛けている)という声が各房室のあちこちから上がるという設定でした。「白名単」(ブラックリスト「黒名単」に対する言葉遊び)つまり「名前も持たない人たち」が、死刑囚を送るときに「メイフェイ眉飛サー色ウ舞」という言葉にならない言葉をあげたという幻聴です。
陳:想像して自分が書いているうちに、自分が感動してしまうんじゃないですか。
桜井:それはありませんが、自分がそれを書いた瞬間、胡冬竹さん(台本の翻訳者)に送ったら、それで終わり。その日本語は消えてしまいます。送った瞬間、日本語台本は不要なものになっている。これは奇妙な感じでした。これは「天使」性でしょうか。天使は神の前で讃歌を歌ったあとにすぐに無に帰るといいますから。台本など残る必要のないものですが、俳優がその言葉を食べてそれを場に返還した瞬間は残ります。昨日、現実にもっと大きな出来事(中国の「反分裂法」に反対する3月26日のデモ)があったけど、芝居の一瞬はやはり勝ってしまう可能性もあります。それは文学を読んで、忘れられない数行に接することと同じだと思います。
陳:小説は本の形で残るのですが、演劇は毎回の公演の解釈が違うし、やはり脚本は大事ですね。演出が違っているからこそ、元の台本も大事ですね。
桜井:実は、僕の台本は今まで一回も再演したことがないのです。さっき言ったように、その参加者(俳優)の現在に合わせて書きますから、再演が不可能なのです。
陳さんが六十年代に『劇場』という雑誌を作った話を聴いたことがあります。陳さんはモダニストといわれた時期があるのですか。
陳:六十年代のとき、レットパージと戒厳令の下で、モダニズムには二つの機能があった。一つは、現実に触れないようにする機能。社会、人間、問題に言及しない。当時の「反共抗ソ」文学は、命令的なもので退屈だった。もう一つはアメリカに影響されたもの、合衆国情報サービス(USIS)、全ての冷戦文化はアメリカを中心で、各地のUSISを通してアメリカ式のモダニズムが輸出された。だから、そのときの若者はその影響を受けた。劇場関係者もそうだった。そして、劇場関係者は内部から分裂した。劉大任という人がいたが、やはり僕らと思想的には違っていた。僕らはリアリズムを主張して、結局雑誌『劇場』は分裂の局面を迎えた。
今日は本当にいろいろと教えていただきまして、テント芝居の魅力を感じさせられました。僕は本当に簡単なことでも感動するのですよ。それも、まさに劇場の不思議な魅力ですね。
桜井:日本のアンダーグランド文化というのは、ほとんど資本に回収されちゃったのです。だから、僕らがやっているのは、墓地から死者を掘り出すような領域です。そういう領域はありがたく残っている。かつて西武資本は六十年代にいち早く劇場空間に目をつけた。特に、戦略としてアングラを使用しようとしました。
陳:戒厳令が解除された時期の台湾でも、似たケースがあった。
桜井: 70年代に西武から僕らのところに誘いが来たことがあります。しかし、僕らがそこから逃れることができたのは、天皇がいてくれたからです(笑)。僕らの芝居は天皇の首を切ったりするような直截な表現があったのですが、担当者が勘違いしたのでしょう。まあ、天皇のおかげで回収されずにすんだということでしょうか。
陳:天皇のおかげで、芝居を残すことができた(笑)。
桜井:70年代は特に天皇を俎上にあげるのは、ある種タブーでした。もちろん今もそうでしょうが。
陳:台湾の場合に、戒厳令の時代に演劇がなかった。戒厳令の解除以降は小劇場が一気に出たが、すぐに資本に買収された。だから、日本のアンダーグランド演劇のような闘いの経験はないですね。
桜井:当時の右翼は、僕らなど相手にしないですよ。公演前に、電話がかかってくるだけです。「お前らは天皇様のことを馬鹿にしているらしいな!」と。「はい、しています」と答える。また「これからいくぞ!」と言うから、「どうぞ、お待ちしてます」と応えた(笑)。
陳:やはり、日本の戦後と台湾の戦後は全然違いますね。
桜井:70年代中頃、天皇が乗っていた列車を爆発しようとした計画した反日武装戦線というグループがあります。それに呼応する形で芝居を作りました。しかし、共産党だけでなく新左翼からも難色を示されました。右翼ばかりか、僕らは左翼からも無視された。
陳:そのときの日本の状況に関して、よく分からないのは、どうして日本の共産党と社会党が全部つぶれてしまったか、ということ。しかも、桜井さんたちは左翼からも排除された、ということ。それらは、教条主義的な発想によるものですか。
桜井:アナキストという認定ですね。たしかに僕などは左翼的な教養がありません。ある種の倫理みたいなものを抱えて右往左往していただけです。当時は、大学に行くこと自体すごく恥ずかしいことでした。そんな牧歌的な倫理観から始まって天皇やアジアに近づいていきました。でも、さっきも言ったように国内植民地的な位置にある寄せ場や被差別部落などで「芝居の奪い合い」をしていると、その倫理を越える何か、つまり思想らしいものが芽生えてきます。それはいわば左翼以下の思想です。
最後にもう一つ。陳映真さんの最近の小説『忠孝公園』(本省人の老人と外省人の老人の友情とそのスレ違いを歴史化した作品)を丸川さんから紹介されて、去年『台湾ファウスト』の参加者に読んでもらった。台湾の仲間は小説の存在は知っていましたが、だれも読んでいなかったですね。日本経由の陳映真です。この小説を媒介にして随分話し合いができました。その成果はこの芝居の中に出てきていると思います。陳映真さんの小説は、今回の芝居の大きな基盤になっていた。まるであのテントの下に埋まっていたかのように、現場でいろいろな作業をするとき、陳さんの姿が見えてきたのです。
陳:光栄です。今日はいろいろと教えてくれて、ありがとうございました。
桜井:こちらこそ、ありがとうございました。
(2005年3月27日、台北にて)
西洋近代の夜明けにゲーテによって表現された「ファウスト」という人間像は、西洋のみならず非西洋においても、資本主義世界を生き抜く人間のある種の規範となっている。簡単にいえば、それは自我拡大の欲求であり、人類の進歩への信頼である。だが、おうおうにして自我拡大とは他者の喪失であり、進歩とは歴史(自己を成立させたもの)の忘却である。
この演劇において「台湾ファウスト」とは、かつての国家テロリズムの中で自由と民主を希求したある種の人物たちのことであり、また、現在開発中の「新薬」の名前でもある。その新薬は、監獄跡地と公墓跡に建設された国立の秘密研究所で発明された、延命作用と頭脳活性化作用を併せ持つ薬だ。優秀な個人を多数輩出することが「台湾」の延命となるだろうか。また、苦難の末に得たには違いない現在の自由と民主は「台湾」を未来と過去に開くことができるのだろうか。
この演劇の時間は、名簿にすら載らないおびただしい死者たちのさまざまな声と輻輳しながら、進行しまた滞留するだろう。
付け加えると「企画」として名前を冠している「海筆子」とは集団名ではなく行動名である。台湾を拠点としているが、台湾人のためだけのプロジェクトではない。地理的に東アジアと呼ばれる領域、南シナ海から台湾海峡、東シナ海、黄海から日本海を漂う「水草」をイメージした名称である。「水草」のような寄る辺なき者たちの弱い力=身体的表現が、この地域の近代の歴史性や現在の地政学的な状況といかに格闘し、そこにどのように介入できるか。これを仮説することが、この「劇場」の目指すところである。
「台湾ファウスト」プロジェクトにいたる経緯と「新しい公共性」について
このプロジェクトは2年前に、日本人である桜井大造から発案されたものだ。、1999年に、桜井は日本劇団「野戦の月」を率いて、三重市の河原でテント演劇「エクソダス(反核害記)」を公演した。その翌年、差事劇団のテント演劇「記憶的月台」の演出、また引き続きテント演劇ワークショップを行ったり、秦kanoko舞踏公演に参加するなどして、台湾の表現者たちと共同してきた。
東京の劇団「野戦の月」で日本公演を続ける一方、台湾に「海筆子」という台湾人との共同行動の企画名称を持ち、1年のうち約3割は台湾に居住することで、台湾をもう一つの活動拠点として、このプロジェクトの実現を推進してきた。
桜井が台湾を活動の拠点としたのは、ポストコロニアリズム状況の中での、帝国主義本国人としての身の処し方である。長年、朝鮮と日本との歴史的関係と韓国の民主化闘争への具体的関わりの中で<表現>を続けてきた桜井にとって、90年代に台湾との遅すぎる出会いが、差事劇団の鍾喬を通じてあったのである。
芸術というものが「深い反省の形式」であるとするならば、演劇ほどその反省の深度を試されるものはない。そこには、現実を生きる人間たちがさまざまな歴史性をかかえ軋轢や摩擦を起こしながら存在するからである。
そして、現実的には不平等であり非対称的な存在である者たちが、どのように<対等性>を獲得して劇場という一つの場に存在できるのか。このことが演劇における最大の難題であり、もっとも重要な問題意識なのである。もし、演劇という場に対等な関係性が作動していなければ、「反省」は偏狭なものとなり、あらたな抑圧関係を再生産し、再び「反省」の種を作るだけだからである。
対等であるためには、相互に自立していなくてはならない。自立とは強大な<世界>とただ一人で向き合うことである。自分を卑下せず切り縮めずに、<世界あるいはその権威>の前に立ちつくすということである。
今回、私たちのプロジェクトは、公共からの一切の助成を求めない。なぜなら、国家やそれに準じた財団による助成とは、単なる金銭の貸借・贈与ではなく、同時に「権威」の貸付を伴うからだ。私らは、今回の自らの共同行為を、そのような「権威」によって補完することを望まない。なぜなら貸し付けられた「権威」は、私ら自身を旧来の姿のままに据え置くアイデンティティにつなげてしまうからだ。
いま、私らはどのような「権威」が貸与する衣服をもつけずに、丸裸で出発しようとしている。これは台湾の現状においては、特別な事だろう。金銭の問題だけではなく、私らの行為を保証するものが、どこにも存在しないということだからだ。自分らで相互に自分らを保証しあうしか方法がないのだ。私らの手元にあるのは「対等な関係」への希求とそれを支え合う「信頼関係」である。
私たちはこの場をとりあえず「新しい公共性」と呼ぶ。国家に委ねられてきた公共性とそれの持つ正統性。その正統なる公共性の上に劇場を建てないということが、今回の私たちの<表現>における意志である。それは観客やテントの建つ近隣住民との関係においても同様である。観客や近隣住民もまた私らの<表現>を何らかの権威や既成観念の上に安住して見ることができない。つまり、私たちの場は<サービスと消費>あるいは<権威の押し売りとその受容>の関係にはないということである。
だが、「新しい公共性」は簡単に発明・発見されることはないだろう。ああすればいい、とか、こうすればいい、といった<場>の言及性とは一番遠いところにあるのだ。私たちのあらゆる「知恵」が動員されなくてはならないが、その「知恵」は私らの作業する「手」との協働において絶えず確認されなくてはならない。ここでいう「手」とは、私たちの亡くなった親たち(肉親という意味ではない)や、まだ生まれていない子供たち(肉親という意味ではない)と結び繋がっている「手」のことだ。
そして何より、現在の自分自身ムム何の権威もなくどんなアイデンティティからも排除されているところの自己ムムを、<世界あるいはその権威>と対峙させることからしか出発できないのだ。それは演劇という場とそこに参集する者たちが挑戦しなくてはならない、「反省の形式」なのだ。
(マスコミ用文章より)
テント公演「台湾ファウスト(仮題)」への長い道のり
野戦の月・海筆子 桜井大造
現在、台湾の仲間たちと 05年3月の「台湾ファウスト(仮題)」テント公演(台北市)をめざして準備に入っている。これは「野戦の月・海筆子」と台湾の民衆劇場「差事」の合同公演というのではない。台湾人を中心とした、あくまで個人参加による「共同」行為としてのテント公演である。昨年来の呼びかけに応じた約20名くらいのメンバーたちと、これまでに7回ほどのミーティングを行ってきた。最初に企画し、呼びかけたのは「日本人」である筆者だ。
当初、呼びかけは簡単なものだった。
・「共同」でテントを立ち上げよう。「共同」であるためには対等な関係性を保証しあうこと。
・所属している集団とは関係なく個人の意志で参加すること。
・台湾政府から一切の援助を受けないで、観客の入場料収入だけでまかなうこと。
・したがって、役者・スタッフは無報酬であること。
・会計は公開すること。
・公演にいたるまでの過程で話し合ったことは、できる限りの方法で公にしていくこと。
予想通り(というべきか)、これらの基本的な点を巡ってだけでも、会議はきわめて紛糾した。特に、政府の資金援助を受けないという点については、「何を言っているのかわからない」「政府資金は民衆が使うべきお金だ。私たちは民衆演劇をしているのだ」「ここは日本のような第二世界ではない、第三世界なのだ」「それは商業主義なのか? アマチュアリズムなのか?」などの疑問や反対意見があった。
通常、台湾のパフォーマンスはほとんどすべてが政府からの資金援助を受けている。どのような小さな小劇場においても、微かな額を得るために大部の計画書を作成し、報告書を作成するアドミニストレーターという涙ぐましい人物がいるのだ。そして、日本や欧米のパフォーマンスが国立劇場で行われる際には、それと比べるべくもない巨額なお金が簡単におりる。
ちなみに、99年に「差事」に招請され「野戦の月」が台湾公演した際は、私たちは自費で行くことに決め、「差事」に対し、文化局に資金援助を申し込まないように要請した。台湾政府から援助されるいわれは、私たちにはないからだ。
このクニでテント芝居を続けてきた身からいえば、クニから資金をもらうなどというのは、機動隊に思い切り頭をかち割られよほど打ちどころが悪く、でもなければ湧いてこない発想だが、彼らの反対意見は、鼻先で一蹴できるほど簡単な事柄ではない。
たとえば、フィリピンの民衆演劇のメンバーたちは、自らをカルチュアル・ワーカー(文化労働者)と呼び、その社会的地位は極めて高い。民衆劇場の指揮をとれるのは、大学卒の文化エリートたちなのだ。
筆者の偏見に満ちたミンダナオ島の見聞でいえば、カルチュアル・ワーカーたちはいつもきわめて意気軒昂であって、パフォーマンスの始まる前には必ず1時間近い演説をする。内容の説明を含め、そのパフォーマンスの意義をえんえんと啓蒙するのだ。「啓蒙かー」とつぶやいたら、会場では「エデュケーション!」の声がとどろいた。
その時のパフォーマンスだが、彼らはミンダナオ島だけで200くらいあるといわれる各先住民の村に入り込み、文化を保存(?)するため、その歌や踊りを蒐集してくるらしい。国が主催する演劇フェスティバルで発表するためだ。当然、それは大舞台にのせるにふさわしく洗練(?)され、赤面するのもはばかるようなブロードウエイ・ミュージカルのイミテーションのようなブツに昇華(?)されるのだ。終幕に当の先住民が舞台に昇る、ただ頭を下げるために。そして大拍手。それはなんとも居たたまれない場景だった。
だが、「戦後賠償どころか、冷戦期を居直り強盗のようにして収奪の限りを尽くしたジャパニーズー帝国主義本国人」に批判される筋合いなど彼らにはないだろう。そんなことより、来年のフェスティバルに来てくれないかとのお言葉。口ごもっていると、国際交流基金やセゾン財団などからこいつらはいくらぐらい金を引っ張りだせるか、品定めしているご様子。鋭い眼光に目を伏せると、まるっきり無能力であることを見て取って、さっさと行ってしまった。話しの通路などまるでないのだ。
台湾に話を戻そう。反対意見に対して「とりあえず」筆者は原則的に対応した。
既存の公共性の枠内では、私たちは対等な関係(平等ではない)に基づく「共同」を達成できないと考える。私たちは民衆のためにテント劇場を立ちあげるのではなく、民衆として、あるいは、民衆とともに「テントという場」を開くのだ。それは私ら自らの知恵と手で、新たな公共性を発明あるいは発見することでなくてはならない。いや、「新たな公共性」という言い方は語弊がある。おそらく、それは「新たな」ではなく、ずっと存在していながら開かれることを拒まれてきた「公」であるはずのものだ。それを、私たちは既存の公共性という敷石をひっぺがえして、あらわにするのだ。もちろん、そのような場が現れたとしても、「テントという場」にあっては、それは一瞬の体験に過ぎないだろう。けれども、その体験とは、既存の公共性(世界)の中に身を縮める「人質」のような私らの身体を、違う可能性の方に開くものではないか。あるいは、世界そのものを変えていく可能性の一方向をかすかに示すものではないか。
このような原則的な物言いは、彼らの疑問に十分に応えうるものではないのだが、彼らも「とりあえず」受けとめてくれた。この後、議論は「台湾とは何か?」「民衆とはだれか?」といったテーマに移っていく。
4月、濱村篤が陳映真氏の小説「忠孝公園」と丸川哲史氏の評論「リージョナリズム」をもとにレポートした。簡略にいえば「忠孝公園」は、二人の老人の話である。「満州国」の日本軍特務から国民党の特務に転身し台湾に渡ってきた外省人老人と、日本軍軍属としてフィリピンの収容所の看守をしていた南部の農民である本省人老人。彼らは、晩年、同じ公園で顔は合わせながらも、まるで交わる可能性がない。2000年に陳水扁本省人政権(民進党)が誕生すると、手錠を後ろ手にはめたまま外省人老人は自死する。一方、本省人老人の方はホームレスとなった息子がいるが、彼を最終的にあきらめ、孫娘の連れてきた青年をも怒鳴りつけることで、完全な孤独の中に墜ちていく。この小説と丸川氏の「リージョナリズム」の叙述は、まるでツインのように重なるものがある。
それはともかく、濱村篤の長いレポートが終わったあと、参加メンバーの何人かが、次々と自分の生い立ちや父母の身の上を語り出した。それは唐突だったし、会議の場はすでに尋常ではなかった。人前で父親のことを話したことなどない、と言って話し始めたのは外省人兵士の父と台湾人の母をもつAだった。父母が白色恐怖で外国に行ったまま戻らなくなり、祖母に育てられたという客家人のBの話。台北の淡水河をはさんだ下層の町、零細工業地帯・三重(サンチョン)ーー野戦の月の台湾公演はここの河原であったーーそこで中学から働き続けた労働者本省人のC。原住民アミス人のDの話は、徐々にうなり声になり、時に地鳴りのような嗚咽となった。その顔は、南方戦線、皇軍高砂部隊に徴用され、怪我し飢え戻らぬ人となった叔父たちの慚愧の念がそのまま憑依したかのようであった。
その日に錯綜した「感情記憶」の噴出は、彼らの親たちの世代の代理的な表象であった。しかし、逆にいえば、「忠孝公園」に描かれているように、親たちの世代がこのように「感情記憶」を交叉・錯綜させるような「場」はありえないのだ。おそらく、私らが開こうとしている「公」とは、このような錯綜した「感情記憶」の箱をひっくり返し収拾のつかない状態を招来してしまう危険を抱えているだろう。それは危険ではあるが、その危険は私らには必要なのだ。なんとしても、私らのテントは、その噴出を相互に見据えるような自己批評的な場として成立させなくてはならない。
このことと大いに関連するが、呼びかけの際の一つにあった「公演にいたるまでの過程で話し合ったことは、できる限りの方法で公にしていくこと」の具体化として、5月23日にシンポジウムのようなものを台北で開いた。テーマはずばり「感情記憶」である。
外部からは、「台湾ーーポストコロニアルの身体」「リージョナリズム」などを上梓している日本の丸川哲史氏、台湾からはカルチュアル・スタディーの過激な研究者である陳光興氏を招いた。まだ、名前すら決められずにいる「台湾ファウスト(仮題)」のメンバーからは、差事劇団の鍾喬、殖民社の王墨林、日本から参加しているドイツ文学研究者・濱村篤、それに筆者が加わった。場所は、差事の稽古場で参加者は約40人。
シンポジウムなどというとお行儀のよい場を想い起こすだろうが、ねらい通り(というべきか)、かなり剥き出しで収拾のつかない話し合いとなった。ゲストの二人に頼んだテーマは、丸川氏には「空間的意識の再編成」という観点から、「東アジアにおけるリージョナリズムについて」、陳光興氏には「時間的意識の再編成」から「台湾の歴史的現在について」である。他のパネラーはおおむねこの2つの軸に沿ってコメントするという立場にした。
詳細は省くが、丸川氏はどんな台湾人よりも圧倒的に台湾の歴史に詳しい人物であり、詳細な歴史的事例をあげながら、また竹内好の「方法としてのアジア」などを引用しながら、東アジアの地政学的な現在とその突破の可能性について述べた。とりわけ印象深かったのは、外省人として台湾にやってきた一人の婦人のエピソードである。彼女は台湾において国語(つまり北京語)の教諭であったが、丸川氏と出逢ったときに突然、日本語を話したという。実は、彼女は日本人であったのだ。外省人で日本人ーー丸川氏によれば、このような例は珍しいことではないという。無数のナラティブが東アジア地域を交錯しながら彷徨っているのだ。
陳光興氏は、脱植民地化と脱冷戦の絡み合った2つの動きから、台湾における歴史的な現在を語った。脱植民地化に向かう運動は、1950年の朝鮮戦争に始まる冷戦によって完璧に抑圧されたこと。脱植民地化運動が再び開始されるのは、40年後の1990年であり、40年の歳月が流れていること。ここに台湾のポストコロニアリズムの現在が絡んでいる。
しかも、脱植民地化の動きは本省人の中には切実な感情記憶として構造化されているのだが、外省人にとっては理解しがたい感情であること。また逆にいうと、台湾の冷戦の終結といえるのは、2000年に民進党が政権を握ったときである。国民党が政権を握っていたこの20世紀の終わりの年まで、基本的に国共内戦は継続していたのである。脱冷戦に向けた運動はまさにこの今の課題なのだが、これもまた、本省人と外省人とではまったくその記憶がかみあわない。本省人にとって国民党とは支配政権であり、国共内戦という意識にはほとんど無縁である。外省人の中にある、故郷を追われ、蒋介石敗戦亡命政権と一緒に逃走してきた悲哀の感情記憶は、本省人には理解しがたいものである。この平行に交わらない台湾における主要な2つの感情記憶を和解させる方法はあるのか、というのが問題意識であった。もちろん、ここではあえて、客家人の存在や11ある原住民集団の問題は省いている。これらのエスニシティ集団が絡んだ場合には、感情記憶の構造は、より一層複雑な様相を示すだろう。
その後のフリートーキングは、やはり省籍矛盾の方向なき方向に向かった。会場の質問者の言っている意味がパネラーにはわからない、あるいはパネラーの言っている意味が会場の質問者にはトンチンカンである。まるで収拾がつかなくなるのだった。進行役の鍾喬も何も言わないし、進行役を放棄したかにみえた。最後は、日本人である筆者が、「台湾ファウスト(仮題)」の企画意図と問題意識を少し詳しく述べることで、お開きとした。
台湾の戒厳令が解除されたのは1987年、今からわずか17年前のことである。国民党時代だけではなく、日本統治時代も当然戒厳令下であったわけで、台湾島と台湾人は1895年の日本軍の上陸から1987年までのなんと92年もの間、戒厳令下にあったのである。戒厳令下とは監視社会であり、密告社会であった。今、30代以上の台湾人なら、その時代の身体感覚は逃れようのないものとして残っていると思われる。40代以上の人間、特に社会変革の希望を持ったことのある人間にとっては、その恐怖はカラダの隅々にまで刻印されてしまっているように思われるのだ。省籍矛盾における「感情記憶」の問題と並行的に存在する「戒厳令の身体」は、私らの「テントという場」でどのような身体として<表現>されてくるのか。それが、自己批評的に<表現>されてくる可能性は、どのような「公共性」の再発見によってか。
これが8月から始まる稽古の現場における、具体的なテーマとなるだろう。たとえば、どこからか監視されていることを意識している身体は、逆に必要以上に、外向きに自分を顕してしまう身体である。自分の潔白を立証しようとする過剰な身振りなのだ。そこには、ほのめかすような要素はまるでなく、余裕なくただ見せつけるような姿勢が際だつ。それも台湾的な身体であることを役者自身、スタッフ自身が見つめることができるか。そこがまず第一番目の勝負所となるように思う。
闘いは始まったばかりである。
(独火星急使2 より)