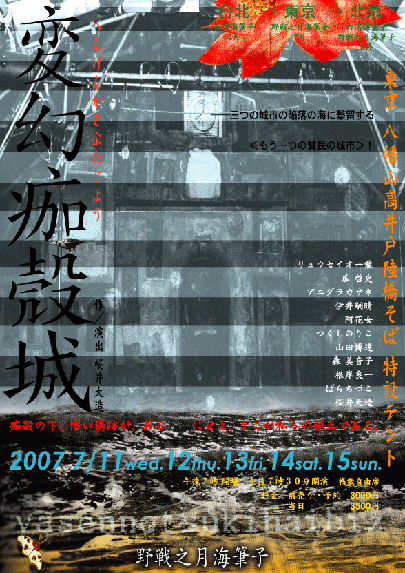作/演出 桜井大造
京王線八幡山駅そば高井戸陸橋下特設テント
2007 7/11(水)12(木)13(金)14(土)15(日)
痂殻の下、惨い傷跡が、ある――にせよ、そこが私らの領土である。
演員:リュウセイオー龍 瓜啓史 崔真碩 伊井嗣晴 阿花女 つくしのりこ 山田博達 森美音子 ばらちづこ 桜井大造
舞台監督:村重勇史
舞台美術:長友裕子 中山幸雄
舞台:永田修平
照明:2PAC
音効:新井輝久
衣装:おかめ つくしのりこ 田口ナヲ 新井香代
翻訳:胡冬竹
通信:濱村 篤 水野慶子
イラスト:阿徳峰
宣伝美術:村重勇史
印刷:制作室クラーロ
制作:押切珠喜 阿久津陽子 板橋裕志 プーロ舍
共同製作:台湾海筆子
音楽:野戦の月楽団 原田依幸
お詫び
チラシに名前の掲載されている役者のうち、根岸良一とアニグラカサネは東京公演への出演が不可能になりました。根岸良一は病気療養のため、アニグラカサネは新たな道をさぐるためです。代わりに新星 崔真碩(ちぇじんそく)が参加します。ここにお詫びし訂正します。
この芝居は、今年、台北(4月)、東京(7月)、北京(9月)という東アジアの三つの大都市で、〈同一の台本〉〈同一の舞台装置〉によってテント公演される。
すでに終了した台北版「変幻痂殻城」は〈台湾海筆子〉企画で台湾在住の役者・スタッフによって行われた。北京語を基本として一部台湾語を使用した。
現在準備されている東京版は、テント劇〈野戦之月海筆子〉の日本人役者・スタッフによって行われる。使用する台本は日本語で、基本的に台湾版と同一のものである。
北京公演は、台北版と東京版の二つの芝居を同一のテント、舞台装置において3日間ずつ連続して行う。北京においても台本は、北京の観客の理解に役立つための最小限の変更はあるが、基本的に台北・東京での公演と同一である。
三都市において、同一の台本、舞台装置であるということが、この芝居の特徴である。したがって、この芝居で設定される空間域は、これら東アジアの三つの大都市の様態を複合化・抽象化したものとなっている。「痂殻城」とはその想像された大都市の貧民地区を意味している。
また、この芝居においては時間帯もまた交錯している。たとえば、東京という視点からはすでに40年前の様相に思われることが、北京においては現在進行形であったり、東京においては近未来的であるだろう様相が、すでに台北においては過去の姿であったりする。また、北京の過去の様態が台北の明日を予感させたりするのである。
「二都の物語」であれば、二つの視線の交差点に互いの様相が現れるだろうが、「三つの都」を想定すれば、交差する地点は時に溶け合い分割しがたいものとして、あるいは時に無縁であるといったよそよそしさとして、観察者の感受性は瞬時に入れ替わざるをえない。観察者(観客・演者)は、自らの視点の中に、錯綜する他者性を感ずるだろう。
それは単に複雑なのではない。私らが居住している現実世界の時間帯、グローバル資本主義が強いる時間がすでにそれなのであり、その時間帯は歴史の消去によってこそ成り立っているのだ。しかし、私らはたとえ破片のようなものであるにせよ、歴史を抱えている。消去されえないもう一つの時間帯を抱えていることは自明なのだ。破片となって分有されているに違いない時間帯が、テントという一つの場で紡ぎあい流れ出すかどうか。この芝居、三つの大都市での〈テント場〉の狙いはそこにある。
近年の東アジアの大都市の趨勢は、人間が住み生きる街(領土)の消去に向かっている。人間は「住む」ことから切り離され、経済圏のモザイクの孤独な単位でしかありえない。それは、人間がその生において形づくる最低限の社会性すらが消えつつあるということだ。克服されるべき貧困・飢餓すらが、「脱領土化」されたということだ。
市場だけが唯一社会性を獲得していく。この市場の社会性が発信する情報に従い、人間はこの社会性にただただ柔軟に対処する以外にないのか。柔軟性のみが社会システムに追従できる方策だとされるのだが、実はそれは不可能なのだ。人間は柔軟ではありえないからだ。
市場の社会性を切断しようとする抵抗的な社会の発明は死活のテーマである。この芝居は三つの都市の陥落した底地に逃走することによって、あるいは自身の身体性(貧困)の様態を変幻させることによって、一夜の〈反世界〉を立ち上がらせようとするものだ。
一つだけ日本の観客のために説明させてもらう。
舞台は庚申(かのえさる)の夜である。庚申は旧暦(十干十二支)で60日に一度巡ってくる。この夜、人間の身体に住む三尸(サンシ)という赤い虫が身体から抜け出し、その人間の悪業を月に鎮座する天帝に密告に行くと伝承されている。だから、この夜は三尸(サンシ)が抜け出さないように寝ずに自分の身体の番をする。それは古来からの中華文化圏の伝承・風習だが、農村共同体にとって60日に一度だけ許される酒宴の夜でもある。それは共同体から逃亡者、密告者を出さない黙契の場だったのだろうか。共同体を維持するための知恵だったのだろうか。日本各地に伝わる祭も同様な意図を持つものがあるように思われる。桜井大造
北京にて
桜井大造
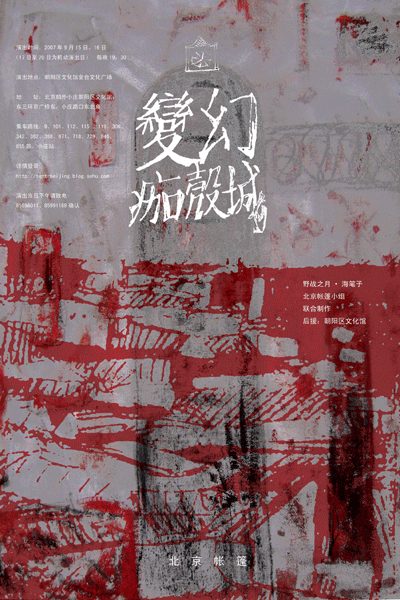
10月、北京に滞在した折り、すでに上演前から話題となっていた「我門走在大路上」という演劇を観た。初演の日である。副題に「近三十年的社会心理史」とある通り、文化大革命の末期から現在にいたる中国国内の社会状況を、二十一人の俳優たちの群像的な動きと会話、時折映写される当時の映像によって編年的に表象していくスタイルの、いわば「構成演劇」である。
編劇の黄紀○氏は、今世紀初頭以来、中国全土で数百回に渡って上演された問題作「チェ・ゲバラ」の作者である。筆者は昨年5月、韓国の光州でこの作品の第二バージョンに出逢った。女性ばかり八人が登場するこの劇は、筆者が初めて接した中国本土の演劇であり、ある意味で衝撃的であった。もちろん、中国語の科白も韓国語字幕も理解できない身であるので、この作品を正確に受容することはできない。したがって、誤読以下のただの感慨にすぎないのだが、あえて書き記せば、その衝撃は当初、八人の女優たちのあまりに小綺麗な身体(身振りと発語の仕方)と、軽やかな演出手法からやってきたものだ。一切の泥臭さを排除したその表現は、まるでコマーシャルフィルムの中にいるような快適さと不気味さを感じさせた。
これが現代中国の最先端にある演劇表現であるとすれば、中国社会の消費社会化は予想以上の進展を見せているのではないか。消費社会化の中で、上昇感覚と挫折感覚に激しく引き裂かれているであろう中国民衆の、その上昇感覚だけが女優たちの身体とそのスピーディな舞台から浮き出てくるようにも見える。だが、さらによく目をこらせば、彼女らの足取りはかなり確かで重心も低い。単に浮遊しているわけではないのかもしれない。一見、何の変哲もないモダニズム表現の身体としか思えないのだが、その影にじっと撓っている何かがあるのではないか。それは、民衆の挫折感覚であり中国型リアリズムの身体なのではないか。そんな気もしてくるのだ。
先月の「我門走在大路上」は、同行した胡冬竹氏に通訳してもらいながら観ることができた。おかげで内容は多少把握できたのだが、やはり筆者が注目せざるを得ないのは、昨年以来、気にかかっていた俳優たちの身体のほうである。若い俳優が多いせいか、「歩く」ことを基本形とした俳優たちの身振りと発語は、昨年以上に小綺麗であり、たとえれば黄河の泥水を繰り返し濾過したかのように明瞭である。昨年筆者が幻視したあのリアリズムの身体は、もはや劇場に入ることすら許されていないのだろうか。快適さと不気味さを二つで一つとして見物しているうち、ふと、フラットな舞台を三方から囲む観客席をながめてみた。そして、はっとしたのだ。観客席のうす暗がりの中に、あのリアリズムの身体を見たように思ったからだ。観客たちの眼差しは一様に鋭いものだった。中国現代史をテーマとしているという衝迫力にもよるのだろう。現代史の記録と記憶の相剋に目眩きながら、しかしじっと瞳を凝らしているように思われる。やはり、それはリアリズムの目玉である。おそらく、この作品はそんな観客席の眼によって幾度となく噛み砕かれ、変容を繰り返し、昨年のあの作品のようにリアリズムを影のように撓わせていくのではないか。俳優たちの小綺麗で明瞭な身振りと発語は、再び泥と交わって黄河にもどるのではないだろうか。演劇という行為をさらに行動させ、本来の人々の居場所に帰すのはやはり観客なのである。筆者が北京のその公演で発見したのは、つまり「観客」であった。
今年、台湾と日本で公演を持った筆者と仲間たちは、果たしてどのような「観客」と出逢ったろうか。その「観客」の眼差しは、私らの小さな行為をどの方向に向けて行動させようとしただろうか。いや、逆にいえば、私らの芝居という現場は、「観客」を真新しく蘇生させることができただろうか。私らが用意した芝居は「観客」を蘇生させるための媒介として機能しえたのだろうか。
私らのいう「蘇生した観客」とは「消費者」のことではない。「民衆」のことである。私らの劇場は、記憶と記録の隙間から新たな「民衆」を析出することによってのみ、本来の劇場となる。そして、その析出された「民衆」の眼差しに押されることによって動き出し、次第に消滅しつつ「現実」の中に姿を替えて再帰するのである。